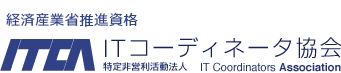| 連載 ITコーディネータ活用記 <実録 京都室町・矢代仁の経営改革>
今後の経営方針の1つとして盛り込んだ「在庫管理強化と、マーケットイン指向による売れ筋商品の品揃え」を実現すべく、矢代仁ではITの活用を主軸とした具体的な展開が進められてきた。 その取り組みは、従来からの資産を生かした在庫管理システムの運用に続いて、販売管理システムの構築へとつながった。 担当ITCの一人であるひかり税理士法人の間宮達二氏によれば、従来のシステムでは「どこにどのような商品があるか分からない」 「社員個々にどのくらいの利益を上げているのか分からない」といった状況だったため、まずは1年ほどをかけて、個人別の売上高や経費、利益率などの統計的なデータが取れる仕組みを作り上げた。そして次のステップで、商品別の統計に基づく売れ筋分析を実現する仕組み 作りが行われた。 「個々の商品に関する在庫情報と販売データを連携させることによって、どのような商品が売れているのか、販売単価はどう推移しているのかといったマーケットの傾向を掴むことができます。しかも、それらの情報を現場だけでなく経営陣もタイムリーに見ることができれば、スピーディな判断と対策が可能になります」と、間宮氏はいう。試験期間中の棚卸し作業で早くも予想以上の成果 販売管理システムの構築については、前回レポートしたように、今年3月にRFP(システム提案依頼書)をまとめ、ベンダー3社の提案を評価・選定した。また、見積り金額の格差に対する矢代仁の驚きも紹介した。 実は、ITの専門家である間宮氏も、ベンダー側の提案にある種の違和感を覚えていた。 「RFPの内容からすると、『本当に必要なのか』と思うような仕様が散見されました。本来なら数多くの組み合わせの中から最適な選択肢を提示すべきなのに、明らかに無駄な投資を勧めていたのです」。 しかし一方で、非常に喜ばしいこともあった。ベンダー側のプレゼンには矢代仁の役員に加え従業員6名も出席し、各社の提案内容をスコア評価したのだが、最も高スコアをつけたベンダーが出席者全員で一致し、最終決定を下すことができたというのだ。 こうして、5月下旬にはプロジェクトチームを発足。システム導入のスケジューリング、旧システムからのデータ移行の準備、新システムのハードウェア発注、一部のカスタマイズを含めた搭載機能の最終決定と設定作業等々を、短期間のうちに慌しくこなしていった。 7月上旬には、旧システムと並行する形で試験運用が開始された。間宮氏によれば、同月末の棚卸しでは、当初の予測時間の半分で作業を完了できたという。 予想以上の効果をもたらした新システムは、8月1日から本格稼働へと移行。その後の日次処理でも目立ったトラブルはなく、矢代仁の業務で活躍している。
| |||||||||||||||||||||||