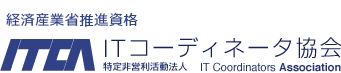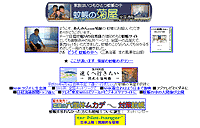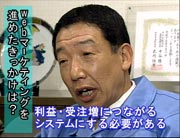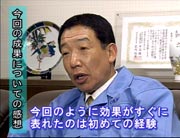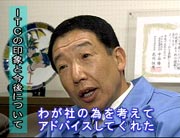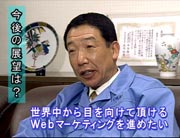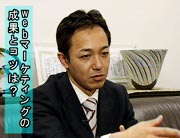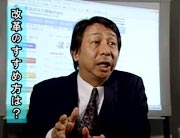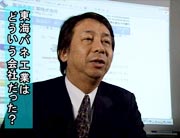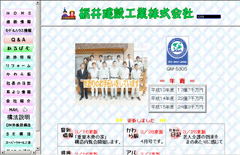|
中小企業支援センターでITコーディネータが活躍 ~ 三重県産業支援センター ~
中小企業支援センターとは? 中小企業経営者が経営上の問題を気軽に相談できる公的施設の中核となるのが都道府県等の中小企業支援センターである。 中小企業支援センターの主な業務は経営課題解決のための相談およびサポートであり、「ここにくれば問題解決の糸口が見つかる」というワンストップ型のサービスを目指している。経営、技術等の専門家を配置し、政府関係機関や商工会議所と連携するなど情報力が高いのも特徴だ。ただ、名称は地域ごとに異なっており必ずしも「○○県中小企業支援センター」とは言わないないので注意したい(県ごとの詳細は、http://j-net21.jasmec.go.jp/link/top.htmlへ)。 このような都道府県等中小企業支援センターの中でも情報化推進を積極的にサポートしているセンターの一つが三重県産業支援センターである。 三重県産業支援センターは津駅から歩いて10分ほどの三重県合同ビル5階にある。館内には各種パンフレットが置かれ、資料の閲覧や会計ソフトの体験利用も可能。気軽に相談ができそうな明るい雰囲気である。 同センターの特徴の一つは、経営相談の専門家であるプロジェクトマネージャーのほかに、ITコーディネータの資格を有する人材を配置していることだ。現在、ITCの水谷哲也氏が、サブマネージャーとして活動中である。 経営相談からECサイト構築まで幅広くサポート 本センターが行っている情報化推進に関する事業のうち、代表的なものは以下の三つ。 ①窓口相談事業 文字通り経営に関するあらゆる相談に応じ、資金繰りや補助金などのアドバイスも行う。水谷氏によると「ITに限らず各種経営相談に応じている」とのことで、第一窓口として分野を限定しない柔軟な対応に努めている。実際、経営者がIT相談にやってきたものの、よく話を聞いてみるとむしろ経営上の改善が急務と判断されるなどというケースもあるという。 ②専門家の派遣事業 IT、小売商業などに関する問題解決のための専門家紹介派遣であり、費用の3分の2が国および県から補助される。「専門化」としてITコーディネータを派遣することも多い。水谷氏は、派遣希望企業にヒヤリングを行い、適切な人材を選ぶこともサポートしている。 ③電子商取引支援事業 これは同センターならではの事業だ。「人口が減少していく中で現在の売上を維持していくために、インターネットによる電子商取引(EC)は今からやっておくべきこと」(水谷氏)との認識で、平成14、15年度にはECに取り組む企業に10万円の補助金を出し、講習会などで指導を行ってきた(補助金は終了)。また、Web上のショッピングモール「バーチャルショップみえ」を立ち上げ、県内企業が手軽にECにトライできる環境を整えた。今後はプレゼント企画などでアクセス数を伸ばすこと、店舗数を現在の2倍に増やすことが目標とのことだ。 三重県はCATVが県内をカバーしており、ブロードバンド環境の先進県でもある。こうしたインフラを活かし、ITを活用した経営革新を支援していく方針だ。水谷氏は「商売上手の方はセンターもITも使い上手。なんでも気軽に相談してほしい」と経営者の積極的な利用を呼びかけている。 本県では、ITCの「経営とITの両方がわかる人材」という強みを活かし、中小企業支援センターに求められる「ワンストップ型サービス」の実現を後押ししている。こうした中小企業支援センターにおけるITコーディネータの活躍例は、今後ますます増加していくことが予想される。 |
||||||||||||||||||||