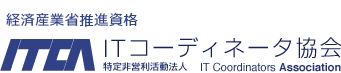現状分析から方針が見えた!取引先を巻き込み在庫削減へ
コンピュータを十分活用できない... 「ここですべての取り組みが決まったと言っても過言ではありません。会社の指針ができ、58年間の歴史の中で一番中身のある年にできたと思います」 IT活用による経営革新の歩みを振り返る睦産業・湯川耕一郎社長の口調が一瞬強みを帯びた。改革プロセスのある地点を境に「大きく変わった」のだという。 湯川社長は過去2、3回、コンピューターを使った原価管理や売上管理にトライした経験を持つ。しかし十分な活用はできず成果は「納品書や請求書を発行する程度」(湯川社長)。苦い思いをしていた。 睦産業が拠点とする広島県呉市は、地域の団体やITコーディネータグループが活発に活動し、相互連携を深めながら企業のIT活用を支援している。平成14年、湯川社長は、中小企業家同友会の縁で社団法人中国地域ニュービジネス協議会(NBC)が主催するITSSP事業(経済産業省推進の戦略的IT化支援プロジェクト)に参加する機会を得た。ITコーディネータによる研修会や個別コンサルティングを体験するなかで、変革の機会をつかんだのだった。 最低限のデータを把握できるようにしたい 同社の事業の柱は大手自動車メーカー・マツダグループへの梱包資材の流通、そして塩化ビニル・ポリプロピレン製の特注文具製造の二つ。湯川社長は特に流通分野において、仕入れや売上のデータを正しく把握したいと考えていた。 現在は6社の委託製造会社を相手に600種類の商品を取り扱っている。背景には「金融機関と普通に話をするには、最低限のデータを持たないといけない」(湯川社長)現実もあったのだ。 担当ITコーディネータとなった溝下博氏が最初に取り組んだのは「社長の思いを整理し、業務フローを明らかにすること」だった。経営課題が明確になるにつれ方針のアウトラインも描けるようになってきた、これなら社員に方向性を明示できる。 「なるほど。そうか」――冒頭に紹介した湯川社長の転機は、IT化の前のこの段階に訪れたのだった。 並行して社内の情報管理をスムーズにするツールとして、販売管理ソフト「商奉行」と在庫管理ソフト「蔵奉行」を導入。基本的な数値を入手できる環境を整えた。 取引先6社の在庫をWebで把握する! そして平成16年からは、第二ステップとして委託生産先企業と商品在庫などの情報を共有するシステム作りに着手した。 同社では、在庫保有数を委託製造先の裁量に任せる商習慣をとっている。取引先企業側では睦産業の出荷情報がリアルタイムにはわからないから、過剰在庫や在庫不足も起こりうる。経営状況を正しく捉えるためには取引先の在庫数を睦産業側でも把握しておきたい。取引先―社外―と連携するにはどうしたらよいのだろうか。 溝下氏からバトンを受けてIT化の第二ステップを担当したITコーディネータの古家後啓太氏、石川敬三氏は「睦産業の納品情報、生産指示がダイレクトに委託先に伝わり、逆に委託生産先の出荷情報が把握できるよう取引先との間をネットワークでつなぐ」ことを提案。取引先の導入負担をできるだけ減らす方法としてWeb技術を採用した。 具体的にはWebサーバーに在庫や出荷情報のデータベースを置く。各社がインターネットを経由してサーバーにアクセスし、Webブラウザーからデータ入力や閲覧を行うという仕組みだ。汎用性のある方式だから今後取引先が増加しても適宜対応できる利点もある。 システム導入の同意を得るため湯川社長とITC石川氏は取引先を何度か訪問し説明を重ねた。その結果、6社全ての参加が実現した。 費用はコンサルティング費を含めて約700万円。湯川社長は「たくさんの方に関わっていただいたことを考えると安かった」という。取引先とネットワークを組むような大掛かりな取り組みは、こうした機会がなければ難しかったかもしれない。 「このシステムで6社の取引先とどのような商習慣が作れるか、どれだけ価値を生み出せるかがわれわれに試される」と湯川社長は決意も新ただ。掲げた目標「3年後に売上2倍、在庫半減」の実現を、地域のサポーターたちは楽しみにしていることだろう。
<ITコーディネータを活用してどうでしたか?> 会社の課題を整理して指針ができたことがまず何よりの収穫でした。 複数のITコーディネータにコンサルティングをしていただいていますが、それぞれの専門分野に基づいた指摘を受けられるので参考になります。情報の可視化など、理解しているが実行できていない観点を提示してもらえるのがありがたい。 (湯川耕一郎社長談) |
|||||||||||||||||||||||||||||||