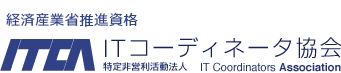卸売が司令塔になり生産指示 100円印鑑で利益を出す!
「印鑑を100円で売る」着眼点がユーザーをつかむ 「そんなビジネスは成り立たないのでは?」との心配をよそに急成長した100円ショップ。店舗では雑貨や食品に混じって印鑑さえも100円で販売されている。印鑑は姓別に一つ一つ商品が異なり、その数なんと5000種類だ。こんな「超多品種超小ロット商品」を100円で売って、利益が出るとは想像し難い。 「北海道の店舗と電話でやり取りしていたら、電話代だけで利益が飛びますよ」――100円印鑑を全国の100円ショップに卸しているクリーク(大阪府大阪市)の谷川英二社長はそう言って笑う。 「印鑑は高い」との思いから100円印鑑を企画したところ、市場は予想以上の反応を見せた。100円ショップには次々と印鑑販売用の什器が配置され、取り扱い店舗は今や約3000店、1日1万本以上が売れているという。誰もが尻込みする「非常識」に挑んだことで消費者に支持され、販売数量を増やすことに成功したのだ。 15000アイテムの煩雑な売上管理をどうするか ただ、この1万本の内訳は細分化されていることに注意しなければならない。例えば「佐藤」「高橋」など多い姓の印鑑はまとまった数の売上もあるが、売上が少ない姓もある。さらに印鑑自体にもボールペンつきなど3種類のアイテムがあり、商品リストは15000に及ぶ。売上や在庫管理の煩雑さは想像に難くない。 しかし、谷川社長は「皆が面倒と思うことを引き受ければ誰からも必要とされる企業になる」と考え、自ら売上データの管理を手がけることにした。自社に販売管理データベースを構築して販売分析報告や生産指示が出せるようにし、欠品や納期遅れの防止に努めた。つまり情報集積によって販売店や製造工場への情報司令塔になることを指向したのである。 そこに不可欠なのはITだった。 ITCとともにWebベースのシステムを構築 取引先へのリアルタイム発注が実現 当初は、データベースソフト「Access」を使って店舗からの発注情報を管理していたが、データ量が増えた場合の稼働状態、利用者への操作教育、バージョンアップの作業量などで課題を抱え始めた。 そこで、考案したのが「特別なスキルなく使え、誰でも世界中どこにいても仕事ができる方法であるインターネット。いわゆるWebベースのアプリケーションを作ること」だった。ブロードバンドでインターネットにつなげばデータ通信料は定額。距離が遠くてもOKだ。また、今、インターネットを当たり前のように使っている子どもたちが社会人になればWebを使ったビジネスはさらに増大するとの思いもあったという。 新システムの構築にあたり、谷川社長はITコーディネータによる助言を検討。銀行の紹介で知った、中小企業基盤整備機構が実施しているIT推進アドバイス事業の制度を使い、ITC大塚有希子氏に約8ヶ月間、コンサルティングを依頼した。 大塚氏が特に注力したのはシステムの客観的な評価の面だ。谷川社長は、「色々なアドバイスをいただいて順序だったシステム化を進められたうえ、一人ではできない正当な評価・検証を受けられたのは有意義だった」と振り返る。 本システムでは、各販売店からメールやFAXで届いた注文情報をデータベースに登録、このデータを元に出荷指示や補充用商品の製造発注を自動的に行う。クリークに商品を納入する製造元は、Webブラウザーでこうした情報をリアルタイムに把握でき、ムダのない生産計画を立てることができる。発注面においても、店舗側のインターネット設備が充実すれば、いつでも自動発注に移行できる体制だ。 生産から販売までの情報を卸売が管理して商品の流れを制御――これが「情報の司令塔」を目指したクリークのシステムなのである。 大塚氏は「取引先からもWebで情報が見えるようにするという思い切りが、インパクトのあるシステムを実現した」と評価する。 そして、本システムには業務の効率化以外にもう一つ狙いがある。蓄積されたデータを分析して、店舗別や日付別の売上データはもちろん、姓別・地域別の印鑑売上などをはじき出すことだ。谷川社長は印鑑販売の様々なデータを資料に店舗経営者への提案や商品ラインアップのアドバイスを行い、取引先との信頼関係を深めて行きたいと考えている。 人が面倒に思うことをビジネスチャンスにする――クリークにはビジネス創造の原点が見える。
<ITコーディネータを活用してどうでしたか?> システムの全体像は自分でイメージしましたが、進めていく際に自分だけでは一人よがりになってしまう。第三者の目で全体的なバランスや完成イメージを見ていただくのはとても大事です。大塚さんには引き続き法人取引を拡大する事業に関してアドバイスをいただいています。(谷川社長談) |
||||||||||||||||||||||||||||||||