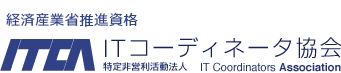| 統一規格のない3次元CADに一工夫 経営分析通じオープン経営の基盤づくり
5000平方メートル近い工場で火力発電所や原子力発電所の配管を設計・製作―広島県呉市のサンワテクノスはスケールの大きいものづくりに携わる企業だ。 「ものづくりの会社がコンピューターというとまずCAD。人をサポートするより機械をサポートするほうに意識が向きますね。私が社長に就任した平成13年以前からサーバーを入れてLANも敷いていましたが、仏作って魂入れず状態と言いますか......」 サンワテクノスの長行事義人社長は、業界が3次元CADへシフトする流れを受け、自社の対応姿勢を検討していた。さらに社内の改革を目指してERPソフトを導入したいという思いを抱き、4年ほど前、ITSSP事業の経営者研修会に参加した。 ところが予想外の展開に。 「IT成熟度の診断を受けて、がっくりきました。LANも入っているし、そこそこと思っていましたが最終図面が手書きだとIT化しているとはいえないとの診断でした」(長行事社長) さらに、導入を企画していたERPソフト(予定費用500万円)の話を持ち出すと、担当のITコーディネータ(ITC)石川敬三氏から「外の標準を当てはめるだけでは業務は変わらない。まず業務の全体像を掴んでフローを作りましょう」との指摘を受けた。 懸案の3次元CADについては、取引先が使用しているシステムに互換性がなく一つの方式を選ぶことができない。一方、すべてに対応できるシステムを構築すると費用が高騰してしまう。よってもう少し時期を見て対応することにした。 CAD、ERPといったシステム導入を一旦保留し、受注から設計・製造までのトータルな業務フロー作成を第一目標としたのである。 ITを入れる前に 業務の全体像を描く 同社でコンピューターの管理やシステム運用を担当し、研修会にも足を運んだ松井俊二氏は述懐する。 「それまで社内では各部門で書類を作成して次の部門に渡していましたが、書式や項目の名称などがバラバラでした。そこで、担当者に集まっていただき、約1年かけてルール作りをしました」 各部署が独自で作成している書類もルールをそろえてデータでやり取りすれば、入力工数やミスが減り、また意思疎通もスムーズになる。同社は従業員の参加によって現状を洗い出し、会社全体の業務フロー図を完成させた。 本プロジェクトは、社長命令で、「担当者は他の仕事に優先してこれを行う」と徹底。これはプロジェクトをやり抜く原動力となったと同時にもう一つの効果も生んだ。 それは、長行事社長が方針として挙げる「オープンな経営」を実現する基礎づくりだ。 「仕事をブラックボックスにせず、透明で皆が状況を理解できる会社にしたい。私のこうした考えを示すチャンスでもありました」(長行事社長) 従業員が参加して自ら考える機会を通して、会社の方針が徐々に理解され始めたのだ。IT活用の前に行う自社の業務分析は、社員が「新しい会社」を肌で感じる絶好の場ともなるのだ。 3次元CAD問題には 発想を転換してチャレンジ こうして立案した業務フローと社内システムだったが、大掛かりな仕様となったため、導入は中期的なスパンで検討することに。 優先すべきは本業の設計を効率化するCADシステムとの判断で、まずは、3次元CADシステムに取り組んだ。 以前とは発想を変え、「お客様からは2次元CADのデータをいただき、そこから3次元のデータを自動生成するシステム」(松井氏)に挑戦。3次元データをそのまま受け取るには対応ソフトが必要になるが、一旦2次元で受け取り、その後に3次元に変換できれば取引先のデータを活かすことができる。 本システムのサポートを行ったITC白石英雄氏は「社内で一番時間を要しているのは設計。ここを短縮すれば生産性が高まり受注量も増やせる。会社全体が良くなっていくはずです」とシステムのねらいを解説する。 開発にあたってはバブ日立プラントシステムズというパートナーを得て、無事システムも完成。他社から一歩抜きん出るシステムが成果を見せることで、オープン経営の担い手となりつつある従業員の意識も、さらに高まることだろう。
<ITCを活用していかがでしたか?> ITコーディネータは「それぞれが得意分野を持つ家庭教師」のようなものだと思います。独学でシステムを構築するのとポイントを教わりながら進めるのとでは結果に格段にの差が出ます。どんなシステムが欲しいかというベンダー向けの提案依頼書(RFP)はITCコーディネータなしでは書けなかったと思います。社内にシステムの専門家を置くのはお金もかかるし、その人が持っている世界に限定されてしまいますから。(長行事社長 談) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||