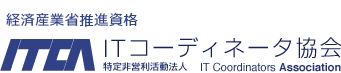「町工場」に組織力をつける! まずはプロセスの可視化から
2代目社長が直面した「町工場」の課題 「この会社は父が35年前に創業しました。田んぼを買い取り整地をして中古の機械を集めて......一から会社を立ち上げるのは、それは大変な苦労だったと思います」 埼玉県志木市、宅地化が進む地域の一角に本社と工場をもつ北光金属の斎藤宏通社長は、1999年に二代目社長に就任した。創業社長は「ものづくりへのロマンあふれる人」。その姿は誰にも真似できないパワーを放ち、別格の存在であった。社長を慕う腕の良い職人、トップダウンですべてを決定してきた社風。そこには日本の製造業に典型的な、しかし、独自に形成された風土があった。 北光金属は電気製品のスイッチなどで用いられる電気接点用の貴金属を用いたクラッド材料を中心に、金属接合用のロウ付け材料、特殊加工を手がけている。例えば携帯電話には1ミリ~2ミリのスイッチ用金属が使われており、1kgの製品で5万台分の携帯電話部品ができるそうだ。主要プレス会社を含め150社の取引先がある。 「風土改革」にITを手段として使う 会社は順調に業績を伸ばし社員数も増えた。すると成長の原動力であった風土は良い面ばかりを見せなくなる。 「職人さんに職位をつけたが管理業務になじめない。社員の管理能力を向上して組織として動けるようにしなければ」――投資を受けている中小企業投資育成のアドバイスもあり、斎藤社長は「第二創業期」を強く意識する。組織力を強化して「町工場」を超えようというものだ。 これまでは仕事がすべてトップダウンで進んでいたため社員は「待ち」の体勢になりがちだった。品質管理が徹底しなかったり、納期が正確に回答できないなどの問題も発生していた。営業職でIT化推進リーダーでもある高富強マネジャーは「今の時代、納期の要求は厳しくなっています。しかし、生産計画が不明瞭なので工場に一つ一つ聞かないとわからない。自分で把握してお客様に回答できないのが問題になっていた」と説明する。 斎藤社長はまず現場改善の5S活動や品質管理の導入に着手、外部研修へ積極的に参加しながら改革に取り組んだ。ただ、いくら座学で勉強しても、会社に戻るとそれを実践できない。「風土を変えなくては...」。斎藤社長は風土改革の必要性を強く実感するに至った。 個別企業ごとの風土に合わせて指導してもらえる中小企業基盤整備機構(旧中小企業総合事業団)の専門家派遣を利用して5S・人事制度改革・品質改革を実行。 そしていよいよITを活用した経営改革の時機を迎える。まずは勉強と、システムに詳しい高富氏がITSSP事業の経営者研修会に参加。そこでITコーディネータの田中渉氏に出会い、引き続き計画書策定コンサルティングを受ける。その後は個別契約を結び生産管理・在庫管理システムの構築へと動き出した。田中氏とともに経営分析から順に会社の現状を見つめていくことで、斎藤社長は「私自身、システムありきの発想だったが、ITは経営課題を解決する手段であることを教わった」。 ITCとともに生産のプロセスを「見える」ように 本システムでは、受注確定の情報を元に生産計画が自動計算され、材料の計算や生産指示書の作成が行われる。作業進捗や必要原材料、製品在庫を一目瞭然にし、「曖昧さをなくすことで経営効率を上げる」というものだ。ただ、金属加工では材料が複数の金属から成る合金であったり、長さがさまざまであったりと、個数で数えられない要素がある。そのため、一般の生産管理システムに比べ難しい点もあるという。今回はさらに最も安い材料の組み合せが計算できるよう線形計算の導入にチャレンジ。「誰にでも全体が見えることを目指した欲張ったシステム」(ITC田中氏)なのだそうだ。 一連のプロセスを経て、社内には風土改革の兆候が表れ始めた。「管理職の社員に『仕組みを作ってそれを守って管理していくんだ』、という意識の変化が見えてきた」(斎藤社長)のである。同社と歩んで2年になるITC田中氏は、「これを機会に経営計画の立案や社内の意識改革を実行することが大切。それをお手伝いできるのはうれしいこと」と、斎藤社長の気概を頼もしく見つめる。 今回のIT化は、北光金属の飛躍の契機になりそうだ。
<ITコーディネータを活用してどうでしたか?> 弊社は創業者のポリシーから外部の専門家には否定的な社風もありました。しかし、実際にコンサルティングに入っていただいたところ、客観的に見ていただきつつ、評論家ではなく会社に踏み込んで分析していただけるので大変ありがたいと思っています。私が何を質問しても、まず黙って話を聞いてくださるので、安心して話ができます。IT活用型経営革新モデル事業に採択されたのも、ITコーディネータのコンサルティングを受けてこその結果と思います。 (斉藤社長談) |
||||||||||||||||||||||||