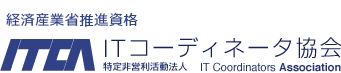更新日:2025年12月26日
ITコーディネータ資格を取得された方のメッセージをご紹介しております。(独立されている方)
その他のITコーディネータ資格取得者の声はこちらからご覧ください。
長井 智章 様(2024年度資格取得者)
私がITコーディネータ資格を知ったきっかけは、企業のIT導入支援や業務改善に関わる中で、「ITに詳しいだけでは経営の成果につながらない」と強く感じるようになったことでした。前職ではWeb制作やDX支援、補助金を活用した事業設計などに携わっていましたが、個別最適なIT提案に留まりがちで、経営全体を俯瞰した体系的な支援の必要性を感じていました。そこで、経営とITを橋渡しする実践的な資格としてITコーディネータを知り、取得を決意しました。
取得にあたって特に苦労したのは、ケース研修での思考整理とアウトプットです。仮想企業の経営課題を限られた時間で構造化し、IT活用を含めた解決策としてまとめ上げるプロセスは、表面的な知識では通用せず、自身の経験や思考の癖を見直す良い機会となりました。一方で、この研修を通じて、経営課題から業務、ITへと落とし込む一連の流れを実務レベルで体得できたことは大きな収穫でした。
資格取得後は、合同会社ZEROSYSTEMを立ち上げ、自社サービスとして中小企業向けAI研修SaaS「BizTeach」を開発・運営しています。ITコーディネータで学んだプロセスは、サービス設計や顧客企業への提案、DX構想の整理に直結しており、支援の幅と説得力が大きく広がりました。「ITコーディネータ」という肩書きは、公的機関や企業からの信頼にもつながっています。
今後は、BizTeachを通じて中小企業の人材育成とDX推進を支援するとともに、ITを単なる導入で終わらせず、成果に結びつける伴走支援を行う存在として、より多くの企業の成長に貢献していきたいと考えています。
岡田 和代 様(2024年度資格取得)
私がITコーディネータを知ったきっかけは、経営コンサルタント養成講座の打ち上げでした。長年フリーのパソコンインストラクターとして活動してきましたが、ITコンサルにも挑戦したいと思い受講しました。しかし参加者は中小企業診断士や会計士など資格を持つ方ばかりで、私だけコンサルとして名乗れる資格がないことに焦りを感じていました。そんな時、他の参加者から「知り合いのコンサルが取得して実務で活用している資格」としてITコーディネータを教えていただきました。
そこから調べてみると、試験は筆記とケース研修の両方が必要で費用のこともあって迷いましたが、業界での認知度が高いと知り思い切って受験を決めました。結果としてITコンサルの考え方を順序立てて身につけられ、新しい知識を得られたことはとても大きな収穫でした。
特にケース研修では、初対面のメンバーとオンラインで話し合い、仮想企業の課題を整理していく流れが実務そのもので、多くの気づきがありました。ひとりで活動している私にとって、とても良い経験になりました。
現在は経営コンサルタントとして、ITやDX、生成AIについて質問されたときにすぐ答えられるよう日々情報を集めています。中小企業が本格的にAIを活用し始めるのはこれからだと思いますし、そのときに役に立てる存在でありたいと思っています。そのため、協会から発信される情報は大変助かっています。これからも資格を持ち続けながら学びを深めていくつもりです。
眞島 悠樹 様(2024年度資格取得)
私は資格取得当時富士通の防衛システムのSIerとして務めておりましたが、現在は独立し、企業が抱えているIT/DX事業の課題解決や新事業立ち上げにおける国際基準適用など、標準化コンサルを主事業とし務めております。
私がITコーディネータを取得したきっかけは自身のキャリアアップとPMPのPDU獲得、さらには勤めている企業がコンサルへの転向を示す中で自身のリスキリングが出来ればと考え、ITコンサルへ向かう資格として取得を決意し、講習を申し込みました。
講習では主に、企業経営論やITコーディネータ独自のフレームワークを使用して、一つの仮想企業が抱える擬似的な課題を分析し、解決手段を見出すといった流れを、実習を交えて学ぶといったものでした。
実習の流れの中で一部持ち帰りとなり次回の講習までに作成しておくといった課題がありましたが、当時は会社員で昇格課題も抱えており業務多忙だったため、時間の確保には苦労しました。土日や勤務終了後に少しずつ課題を進めていきました。実業務で活かせる場面は早々に見受けられたので適宜活用し、日常を通しITコーディネータのフレームワークを学びました。半期ごとの品質KPIの設定やプロジェクト統制の目的目標の策定、お客様のDX構想に活用することが出来たのは大きな成果でした。
最後に、講義内容や実際の講師の体験談もあり、独立の想いが決まり、現在は無事独立を果たし、自身の売りを客観的に評価できたことで開業初月から固定客も付き、おかげ様で継続的収益を得ることができております。今後は自身のさらなるスキル向上と、社会の発展に貢献し、より良い未来を実現する一助となれるよう日々精進していきたいと思っております。
伊藤 明子 様(2024年度資格取得)
私は中小企業診断士として独立開業するにあたり、先輩方のアドバイスからITコーディネータ資格は「必須」と感じていました。前職では大企業のプロジェクトマネジメントに携わっていましたが、分業体制の中で自分の担当範囲しか見えておらず、「経営課題をITでどう解決するか」という視点が不足していたのです。独立を機に、自分のキャリアを体系的に棚卸しし、経営とITをつなぐ知識をしっかりと身につけたいと考え、受講を決意しました。
学習では、単なるIT導入の知識ではなく、「経営戦略に基づいて業務を改善する」というプロセスの重要性を学びました。これまで曖昧だった"IT活用支援"の全体像がクリアになり、中小企業が本当に必要としている支援の形が見えるようになりました。特に、企業の現場に寄り添い、経営者の想いを汲み取りながら課題を整理する手法は、今の支援活動に直結しています。
資格取得後は「ITコーディネータ」という肩書きが、顧客や公的機関からの信頼につながっています。創業支援や中小企業のデジタル化支援など、より広い領域でご依頼をいただけるようになり、自分自身の活動の幅が確実に広がりました。今後は、経営者の伴走者として、ITを"導入する"のではなく"成果を出す"ために活用できる支援者として、さらに経験を積んでいきたいと考えています。
小林 寛仁 様(2023年度資格取得)
私は現在製造業にて代表を務めております。大学卒業後、富士通でバンキングシステムのエンジニアを務めた経験を活かし自社のデジタル経営(ICT化など)に努めて参りました。
また、その傍らで、地元の商工会において若手経営後継者の育成塾のお手伝いとして、経営者としての理念体系、経営計画の立案のアドバイス係に長年携わって来ました。
その様な中、商工会の指導員の方より、「経営者目線でデジタル経営を志向している私のスタイルがITコーディネータそのものではないか、ぜひ資格を取得し後進の指導に役立てるべき」とご指導頂き、資格取得を決意致しました。
資格試験では、IT経営推進プロセスガイドラインを一から学び体系を身に着け、ケース研修では、地元地銀様や大手企業様のシステム部の皆さまとご一緒させて頂き、理論体系の現場への落とし込みを経験する事ができ、貴重な体験となりました。
現在、経営に関するアドバイスやサポートなどを行う中で、私の立場や経験の長さから、どうしても従来の経営者目線の戦略に重きを置きがちではありますが、せっかくの資格取得であり、また貴重な体験を元に理論を体系的に学ぶ事が出来たという財産がありますので、それを十分に活かして行きたいと考えています。
私のこれからの活動が、経営戦略の中にネイティブにデジタル化がある状態が、地方の中小企業、小規模事業者に広く定着していく未来への一助になればと感じています。
杉原 美佐子 様(2023年度資格取得)
独立系と言えばカッコイイのですが、ただのフリーランスです。仕事の幅を広げないと、将来の安定は見込めません。私は会社員を経てビジネスマナー講師、キャリアコンサルタントとして活動していますが、それぞれ限界を感じていました。ビジネスマナーの仕事はコロナ禍で需要が減り、さらに大手が始めたオンライン研修には到底太刀打ちできません。キャリアコンサルタントは国家資格ですが、日本ではカウンセリングに対してお金を払う習慣はなく、一方で77,174人(2024年10月末時点)もキャリアコンサルタントがいるので単価も下がり続けているのが現状です。
仕事は鼎でないと、一瞬で崩れる恐れがあります。次に何をしようか考えたときに、ITコーディネータを思い出しました。設立当初から知っていましたが、当時はリタイア後の仕事と捉えて毛嫌いしていました。若かったので。しかし、自分も年を重ねる中で改めて考えると、ITコーディネータは定年なく働けると気づきました。また、上級システムアドミニストレータを持っていたことも大きいですね。お陰で試験は苦労しませんでした。
仕事柄、多くの社長とお話ししますが、ほとんどは人材と効率化(IT化)の悩みです。今まではITに詳しいキャリアコンサルタントでしたが、ITコーディネータの肩書きがあれば、お客様にさらに安心感を提供できると感じています。ITコーディネータとしてはまだまだ駆け出しです。経験を積んで総合的に経営をサポートする仕事を展開したいです。
梅田 浩二 様(2023年度資格取得)
私は2022年10月に中小企業診断士登録し、2024年4月に独立しました。たまたま診断士実務補習指導員の方がケース研修受託機関の代表を務める方で、その方からITコーディネータ資格について教えていただきました。当時からDXの重要性は意識していたので、企業変革実現手段としてのIT活用推進の役割を担うITコーディネータ資格の取得を決意するのに、多くの時間は要しませんでした。
ケース研修の内容は、診断士が経営診断を行う際の考え方と共通性が多いので、特に戸惑うことなく受講することができました。私はオンラインで受講したのですが、他の参加メンバーとも切磋琢磨でき、また交流を深めることができました。一方、専門スキル特別認定試験は抽象度の高い問題が多く簡単ではないと感じたため、ケース研修とは異なる受託機関が提供する模擬試験を何度も繰り返し解き、本試験に臨んだのを思い出します。
受講してよかったのは、プロジェクトマネジメントの進め方を習得したことに加え、SWOT分析を使った経営戦略の立案からバランスト・スコアカードを活用した戦略実行までの一連のプロセスを、ケースを通じて体感できたことです。戦略の立案と実行をワンセットで学べるのは、おそらく本ケース研修だけではないかと思います。
今後は、中堅中小企業の経営者様に対して経営管理の仕組みづくりや、IT活用による管理会計システム導入などを提案していきたいと考えています。経営支援先の企業様から信頼される診断士になるために、ITコーディネータの資格取得は十分価値のあるものだと感じています。
大石 幸輝 様(2023年度資格取得)
私は静岡県にて経営コンサルタントとして活動しており、事業者様の抱える様々な経営課題の解決を支援しています。ITコーディネータ資格取得のきっかけは、当時通っていた大学院でITCケース研修を受講できることを知り、独立後の仕事の幅を広げることができると考えたためです。ケース研修は「経営とITの橋渡しにおけるプロセス」をわかりやすく理解できる内容であり、中小企業診断士としての独立を予定していた私にとってまさに知りたかった分野でした。本当に受講してよかったと感じています。
資格の取得に向けては、ケース研修を受講してから試験勉強を開始したため、ケース研修と試験内容が繋がってくる感覚があり楽しく勉強することができました。その後試験を受験して無事合格し、2023年5月に資格登録することができました。
経営コンサルタントとして独立してからも資格が生きる場面が多く、公的機関への登録を始め、資格を見て問い合わせをいただき仕事に繋がることもありました。経営相談員として対応する際にもIT導入に関する相談は多いため、ケース研修や試験勉強で学んだ知識が役に立っていることを肌で感じています。
今後も本資格の取得を通して学んだ知識を活かし、日々の活動を通じて「経営とITの橋渡し」に貢献していきたいと考えています。
武田 邦敬 様(2023年度資格取得)
私はデータ経営コンサルタントとして、クライアントと伴走しながらデータドリブン経営を支援しております。現在は、大手企業様向けにデータ分析チームの伴走支援やDX研修を行いつつ、中小企業様向けのDX支援も行っております。
独立前は、ITベンダーのデータサイエンティスト兼マネジャーという立場で、社内外のデータドリブン経営を支援していました。私たちはデータが十分に活用されていない業務領域をターゲットとしており、人事・医療・製造・公共など様々な分野を経験することができました。
こうしたプロジェクトに取り組む中で悩みの種だったのが、KPIの設計でした。データ活用が十分でない組織ほど、KPIがあいまいだったからです。そこで、事業起点でKPI組み立てのノウハウを探したところ、ITコーディネータのプロセスガイドライン(PGL)に辿り着きました。2021年ごろからPGLを読んで業務に活用していました。
一方で、データドリブン経営を実現するポイントは、組織文化ではないかと思うようになりました。データ分析は組織の思考プロセスに埋め込まれてはじめて機能することを痛感したからです。
そこで、ITベンダーという立場で外から支援するのではなく、伴走しながらデータ経営を支援すべく独立することに決めました。独立準備の一環で2023年にITコーディネータ資格に挑戦。ケース研修の内容は素晴らしく、事業戦略からKPI、IT課題への落とし込み方についてわかりやすく学ぶことができました。
独立後もPGLは武器の一つになっています。特に、PGL4.0はデータドリブン経営に向いている印象で、伴走支援でも活用していきたいです。
小財 誓子 様(2022年度資格取得)
私は、販促、商品企画などマーケティングに40数年、「食」関連の仕事を中心に、中小企業のサポートする独立系コンサルタントです。ITコーディネータの資格取得をしようと思ったのは、2020年コロナ禍。顧問をしている水処理機器メーカーのDX化を検討しているとき、自身のスキルに必要性を感じ資格取得に臨みました。
リモートのケース研修は手軽で良いですが、リアルでは休憩やフリータイムの時に交流などできますが、名刺交換や交流もなく研修は終え、もったいないことをしました。試験は苦手な基本問題の暗記、応用問題は、自分の思いと違う回答など、いちいち疑問もちながら勉強していたので、頭に入らず2020年度の試験は不合格でした。
しばらく放置していましたが、2022年になり勉強したことを役に立てたいと強く思い、今度は、試験対策講座や模擬試験を100回以上して自信を付け、合格しました。そして、資格を取得しましたが、自分のクライアント以外にどう活かしたらよいか、悶々としていたところ、昨年「ITCA・自治体ビジネスWG OJT(摂津市)の募集」にチャレンジし、現在OJT中で、見分経験を重ねる機会をいただきました。
今、大阪府能勢町の農事組合法人「能勢けやきの里」が運営する野菜直売所の建物と経営の「建直し」リニューアルを手弁当でサポートしています。アナログ経営をデジタル化へ進め、高齢化したスタッフや顧客に便利に活用できるよう取り組んでいます。
補助金申請にかかる資料作成を通して、数値化が重要。そのためにデータ収集、分析が必要とされ、勘や体感だけで運営していた直売所を「採算の取れるビジネス」へ進化させるために、DX化、ITコーディネータの出番があると思っています。まずは、今年の11月オープンに向けて自分のスキルを活かし、邁進しています。
小田 信彦 様(2022年度資格取得)
私は、現在総合広告代理店を定年退職し一年間の充電期間を置いたのち個人事業主として企業のブランドコンサルティング・プロモーション業務を行っています。定年後起業するにあたり専門分野であったマーケティング分野とデジタルマーケティング分野を主とすることに決めました。
実際経営者にコンタクトしていく中でその企業の強みをマーケティングン視点で見つけていくこと、DX改革支援の一環として業務効率化、デジタル化支援、EDI導入支援などITコーディネータの資格が携わる部分が多くありました。自分の過去の仕事やその中から強みを棚卸するなかでマーケティングの資格はありましたが、デジタルマーケティング分野の強みについて具体的なエビデンスが見つかりませんでした。もちろんGA検定などの資格を持っていましたがもっと幅広いデジタル能力を示すものがありませんでした。そんな中で大学生の間でもITパスポートを取得することが就職活動の一環になっていることを知り、自分も取得に臨むこととしました。その過程の中でさらに中小企業診断士のIT版ともいえるITコーディネータ資格があることが解りよく調べることとしました。
長年デジタル業界に所属し、IPAの研修やセミナーにも参加していましたがITコーディネータ資格については知りませんでした。ただ内容を伺うと研修中心でITパスポートの知識も活用でき、研修制度、所属団体の活動もしっかりしていて、取得後も参加団体を通して知識の積み上げが可能なのも魅力でした。
実際取得したのちもその資格を活かす場面は多く、顧客のマーケティングにあったデジタル化と業務改革の両輪で顧客にマッチした改善提案を実行できます。今後ともこの資格を最大限に生かし、顧客の業務改善に努めたいと思います。