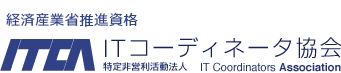更新日:2025年12月17日
ITコーディネータ資格を取得された方のメッセージをご紹介しております。(Sier編)
その他のITコーディネータ資格取得者の声はこちらからご覧ください。
飯田 瑞恵 様(2024年度資格取得)
私がITコーディネータ資格を知ったのは、職場にこの資格を持つ先輩がいたことがきっかけでした。転職やキャリアチェンジ、子育ての節目など、いくつかの変化を経て、これまでSEとしてお客様の課題に向き合ってきた経験を形にしたいと思い、受験を決めました。
以前は販売管理・生産管理システムの現場SEとして活動し、現在はSIerの営業職としてお客様と向き合っています。システムの開発現場で培った経験を活かしつつ、お客様の経営や業務全体を見渡して提案できる力をつけたいと思い、体系的に学ぶ必要性を感じました。
当初、オンラインでのケース研修に少し不安があり受験を迷っていましたが、地元・新潟で研修が開催されることを知り、参加を決めました。研修では実際の企業を題材に課題分析や改善提案を行う中で、これまでの経験が役立つことを実感できました。チームでの議論を通して、多様な視点から学ぶ楽しさや、自分の考えを伝える大切さも学べました。
資格を取得したことで、自分のキャリアに対する自信と新しい方向性を得ることができたと感じています。これからも経営分析や戦略立案の力を少しずつ磨きながら、ITと経営の橋渡しとして、企業の成長に貢献できたらと思っています。
新井 茉莉子 様(2024年度資格取得)
私は首都圏のSIer企業で、ネットワークやクラウド、セキュリティを中心に企業のDX推進を支援するソリューションを提供しています。営業職を経て、現在は企画職に従事し既存事業の成長戦略や新規事業創出の企画・実行に携わっています。
ITコーディネータ資格取得のきっかけは、自社のプロ人材認定制度で本資格が前提となっていたこと、そして中小企業のIT利活用促進に貢献するため体系的に学びたいと考えたことです。ITを単なるツールではなく経営課題解決の手段として理解するため、この資格取得を決意しました。
ケース研修はフルリモートで受講でき、同業の方々と議論を交わす機会が有意義でした。異業種の中でITコーディネータとして立ち回る際の工夫や課題を共有し、多くの気づきを得ることができました。
資格取得後は、ITが経営にどう機能するかを体系的に理解し、自分の言葉で語れるようになったことが大きな成果です。単なるIT導入提案にとどまらず、経営課題を整理し最適な解決策を導く視点を持てるようになり、企業の成長に寄与できる自信がつきました。
今後は、国内の経済活性化や新規事業創出に向け、ITコーディネータとしての知見を活かし、より経営視点で社会に貢献していきたいと考えています。
岩永 優 様(2023年度資格取得)
私は地方のITベンダーに勤務しており、グループ会社の取引先に対して効率化を目的にITの導入を提案する業務を行っております。自社開発のフルスクラッチから世の中にあるパッケージソフトウェア、セキュリティやネットワークのインフラ構築まで幅広い製品を提供しております。
ITコーディネータ資格取得のきっかけは、勤務先より資格取得に対して後押しがあった事と、今まで従事していたIT導入について体系的に学びたいと思いITコーディネータの資格取得を決めました。
コロナ禍だったこともありケース研修はリモートでの参加でしたが、同業の多くの方と交流や議論を行う事が出来たのでかなり刺激的な研修でした。試験に関しては2回受験をし、2回目で合格することが出来ました。1回目は普段業務で行っている事と似ているので大丈夫だろう、と慢心していた事もあり普通に落ちました・・。2回目は絶対に受かろうと思い、教科書や想定問題を何度も行って受かったことを覚えています。
ITコーディネータの資格取得で感じたこととしては上流部分の大事さです。例えば、Aというソフトウェアを入れて効率化する事がわかったとしてもそれは何の為に導入するのか?A以外にB,Cという選択肢があった時には何を以て選定するのか?導入するのは人間なので、上記の様な上流部分の基準や想いの様なものが重要になってくるのは普段業務に接している中でも感じていた事でもありました。
ITコーディネータの資格を学ぶにあたり、そこを体系的に学ぶことが出来ました。この資格はコンサルや上流部分を担う人だけでなく、開発やテストを行っている方たちが全体感を学ぶ為にも有効な資格だと思います。
佐藤 聖 様(2023年度資格取得)
私はITコーディネータ資格を同僚の紹介で知りました。SIerの会社に勤務しており、AIモデルやシステムの開発を中心に取り組んでいます。ITを活用した課題解決のプロとしてキャリアアップの可能性を感じ、さらに調べるうちに、すでに取得していたPMP資格との親和性の高さに気付き、企業のIT活用を支援する役割に魅力を感じて挑戦を決意しました。
資格取得に向けて参加したケース研修は特に大変でした。研修では仮想企業を題材に、IT経営プロセスを実践的に学びました。IT経営推進プロセスガイドラインの適用方法を考えながら、実際の企業の課題にどのようにアプローチするかを議論し、経験を積むことができました。この過程で、理論と実務を結びつける重要性を再認識し、課題解決のための方法論を習得できたことが大きな収穫でした。
資格を取得したことで、自分のスキルに対する自信が深まりました。IT経営プロセスを軸に、これまで経験則に頼っていた課題解決のアプローチが、最短ルートでの提案へと変わったと実感しています。さらに、IT経営プロセスを活用することで、支援対象が明確になり、誰に対して支援を行うべきかがはっきりしました。これまで漠然としていた支援の方向性がクリアになり、具体的な課題に焦点を当てた提案ができるようになったと感じています。
今後は、AI技術とIT経営プロセスの知識を組み合わせ、AIに強いITコーディネータとして企業の成長を加速させる支援を行いたいと考えています。これにより、IT経営プロセスを推進するエンジンとしてAIを活用することで、企業の競争力を高める手助けができると確信しています。この資格を活用し、より多くの企業のIT活用を推進し、効果的な支援を提供していきたいと考えています。
菊池 崇仁 様(2023年度資格取得)
地方のITベンダーで組織・人材開発を中心とする経営管理に従事しています。ITコーディネータ資格は、現職に就いてしばらくして参加した異業種交流の場で、とある自治体のDX担当の方から教えていただきました。現職の事業特性上、クラウドやAIなど先端技術を取り入れたい企業や同業他社の事業担当とは交流があるものの、地方で根強い旧来型のIT活用から抜け切れていない企業やそもそもIT導入がままならない企業との接点が薄い課題があります。経済産業省推進資格として影響力があると考えられる本資格は、その課題を打破しつつ、将来の独立を視野に入れたキャリアアップの土台にベストと考え、取得を決意しました。
試験は「IT経営推進プロセスガイドガイドライン」の徹底的な読み込むとともに、これまでの経験を活かしたことで、短期間での合格が出来ました。その後のケース研修は居住地と実施時期の都合からオンラインでの参加でしたが、首都圏のITベンダーやコンサルティングファーム勤務の方、独立を見据えて取得を目指す方など普段接する機会がない方々と対話し、彼らの知識や経験を通じて接触機会が少ない顧客の考え方を知れて、良い刺激になりました。
現在は取得当時と状況が変わり、現職の組織・人材開発にフルコミットしているためITCとして活躍しているとは言えません。しかしながら、取得までに得た内容はIT・デジタル活用を含めた企業経営全体を俯瞰し、適切な打ち手を導くにあたって基本的な考え方となっています。内外環境に気を配り、自社の企業価値最大化に向けた活動をこれからも続けていきたいと思っています。
村松 真 様(2022年度資格取得)
私はインフラ系システムインテグレータの会社で、サーバー構築やクライアント展開などを請け負うエンジニアをしています。近年は、サーバーのクラウド移行が進み、サーバー構築業務から、クラウドサービスの運用支援に業務内容がシフトしてきました。そこで4年ほど前に中小企業診断士の資格をとり、経営視点を踏まえたシステム運用を提案するようになりました。そうした中で、より広い視点で顧客のシステム構築・運用を支援できるようになりたいと考え「ITコーディネータ」資格取得を目指しました。
最初、ケース研修受ける前に「IT経営プロセスガイドライン」を読んだだけで試験を受けてしまい、見事に不合格でした。「IT経営プロセスガイドライン」ただ読んだだけでは、その裏にある、実践で練られた理論体系の意味が理解できず、適格な回答ができませんでした。改めてケース研修を受けて、実際にワークショップの中でグループメンバーと対話をしながら、フレームワークを完成させていく中で、「IT経営プロセスガイドライン」に書かれているひとつひとつの言葉の意味がわかってきました。グループメンバーとのディスカッションもとても刺激的で、異なる背景や経験を持った人たちがアイデアを持ち寄ることで、課題検討の深みがこれほど増すのかとおどろかされました。
ITC取得後は、中小企業様向けのシステム提案の際に、経営者の意図に沿った説明を加えることで、より顧客の納得性の高い提案ができるようになったと感じています。
今後は、ITコーディネータ兼中小企業診断士として、ITCの研鑽を積みながら、AI時代のシステム運用を支援していきたいと考えています。
安藤 陽一郎 様(2022年度資格取得)
私は、SIerの会社に勤務しています。主にシステム提案から要件定義、外部設計の業務が中心となっています。本資格を知ったきっかけは、上長から取得を勧められて知りました。
お客様へシステム提案する機会が多くなってきたこともあり、経営とITを体系的に学びたいと思い、ITコーディネータの資格取得を決意しました。
まず資格取得のために私はケース研修を受講しました。コロナ禍だったこともあり、ケース研修はリモートでの参加でしたが、常にカメラオンでの研修でしたので、講師の方の表情も伺いながらの研修でした。研修内容も座学よりワークが中心となっている構成で、特に企画書を作成する演習はとても実践に近い形式での研修内容でした。研修中のグループワークでは、異業種の方と知り合うことができ、よい刺激となりました。
私が苦労した点は、研修レポート課題の作成でした。特に「経営戦略企画書」、「IT戦略企画書」については、どのように簡潔にまとめて理解しやすい資料にするのかが難しく感じました。
ケース研修後、資格試験に向けた対策として、1ヵ月間ひたすら「IT経営推進プロセスガイドライン」の読み込みを行い、過去問を解くことによって無事に合格することができました。
この試験対策を通じて、IT経営プロセスガイドラインを体系的に理解することができたため、現在のシステム提案の仕事にかなり活用できています。また、ケース研修を通じて、経営課題を可視化する力が身についてきたなと実感しております。今後は、お客様の企業価値向上を目指して、お客様の経営課題を解決できよう提案活動に努めて参りたいと思います。