|
IT Coordinators Association |
| 東京鋼鐵工業(株) |
作成者:イットアップ(株)
岩佐 修二
ITC認定番号:0002032001C |
作成年月日:2002年5月9日 |
<概要>
東京鋼鐵工業(株)の情報化は、2代目社長の田辺恵一郎氏のリーダーシップによるところが特色です。同氏が大学を卒業した17、8年前に遡り、常に企業の経営課題を直視し、その解決手段としての情報化への取り組みは、決して派手なものではありませんが、実に大きな成果を企業にもたらしています。
失敗も多く経験しましたと田辺氏は述べられていますが、その失敗をも次の情報化の糧にしつつ、企業のあるべき姿に向けて情熱を燃やし続けたことが今日の発展に結びついたと思われます。報告内容は、地味ではありますが、典型的な中小製造業がその時代背景のなかでいかに情報化に取り組んできたかが非常に判りやすく述べられています。
田辺氏と同世代である私も同様に辿ってきた情報化の取組みを改めて思い出させた内容で、共感を覚えました。
<経営課題と解決手段としての情報化>
まず、同社の経営課題と情報化の取組み状況を報告事例から抽出してみると次のように整理されます。
整理するうえで、情報化の基盤作りの時期を第1段階とし、情報の活用の段階を第2段階と分けて考えました。
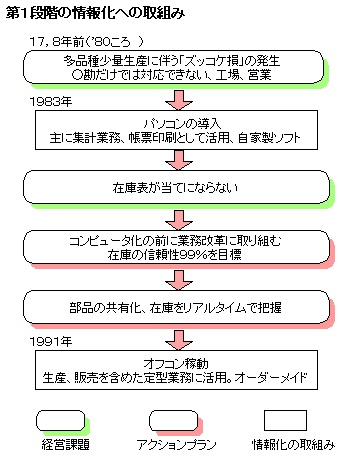
"コンピュータ化の前に、業務改革に取り組む"という田辺氏の言葉こそが、情報化の真髄を表しています。中小企業の経営者の多くは、情報化と言えばコンピュータハードとかパッケージソフトのことを意味し、業務とシステムが密接に関連していることを忘れています。その結果は、システムを稼動させてもその成果を充分に得られないとか、
いつのまにか利用されなくなります。経営者の多くは、何故、投資したシステムが役に立たないのかを理解できません。それは彼らがシステム導入の目的を充分に検討できていないためです。非常に残念なことですが事実です。
当事例は、在庫の信頼性99%を確保することを明確な目標にして業務改革に取り組まれています。私の経験からも在庫の精度を高めるための業務改革は、継続した組織的な活動と経営者の熱意がなければ達成できません。当事例報告ではあまり触れられていませんが、現状の問題点をひとつひとつ潰していき、業務ルールを設定し、
その定着に地道にとりくまれたことと推測します。業務を明確にしルールづけることを繰り返し行うことで、目標値の信頼性が得られます。そしてこの業務実績がコンピュータから出力される数値に反映されるわけです。それが信頼性そのものであり、以後の情報活用化のベースになります。とても大切な段階です。
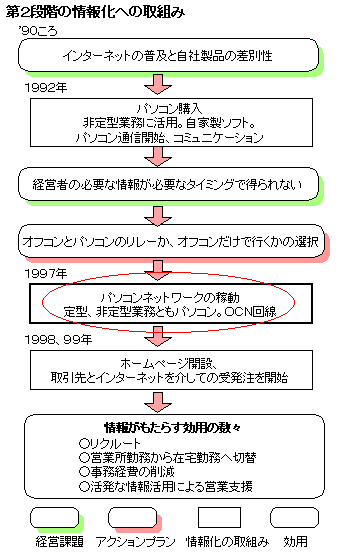
この段階の特徴的な事項は、パソコンネットワークの稼動です。それ以前に、従来のオフコンの資産を継承するか、あるいはパソコンに切り替えるかいう情報化のベースラインの意思決定があり、田辺氏はパソコンへの切替を決定しました。
この切替を決断したことが、以後の情報化の永遠の課題である柔軟性と拡張性を充分に活かせる環境を生み出したと思われます。システムの切替というのは、それまでの作りこみへの思いが強いほど従来のやり方を継承し勝ちですが、将来性を考えた意思決定ができたことが高く評価されます。
<最後に>
当事例のポイントは、上記の2つの情報化のターニングポイントを経営者としていかに意思決定したかという点にあります。結果として正しい評価だったと今でこそわかりますが、その時々で企業を取り巻く環境変化に対応した自社の情報化の方向性を経営者として意思決定することは、相当に緊迫したなかでの決断だったと思われます。これも、ひとえに田辺氏の中小企業の生き残りを常に考え続けたことが動機だったと推測します。
ただ残念なことには、当事例では成果のモニタリングが具体的な数値では示されていませんし、また同社のHPからも公的な業績値を知ることはできないのですが、それ以上の示唆と指針を我々に提供してくれています。中小企業の情報化の成功事例であることには間違いありません。
同社が取り扱うオフィス家具業界は大企業を中心にして、競合が厳しい状況が過去から続いています。最近では、インターネットの普及により今まで以上に競争がより強くなっている感があります。大手企業はその知名度を活かしてマーケットプレイスの場での取引を増す、あるいは豊富な人材を商品開発力に注入しています。そのような競合のなかで、
同社はインターネット技術を活用いたオフィスレイアウトの提案を行うことで差別化し、業績を伸ばそうとしているものと推測しますが、これも、前述の情報化の取組みにより基礎が築かれた賜物と思われます。 |
|