| (株)ダン |
作成者:(株)イットアップ
岩佐 修二
ITC認定番号:0002032001C |
作成年月日:2002年11月06日 |
(株)ダンの成功事例について丸川常務がお話される内容は、システム構築というよりは経営ノウハウであり経営戦略そのものである。
決してITの先端技術に触れることもなく、いかに経営基盤の仕組みを作り上げたかが伝わってくる。我々ITコーディネータが企業のIT化支援をする際に、
最も考えなければ成らないこと、すなわち、"まずは経営戦略を明確にすること。
その経営戦略の実現手段の一つとしてITを活用すること"を当事例では、丸川常務が語っている。
この度事例本文を読み、ダンの情報化への取り組みの原点が、経営トップの次の言葉だったことを知り、改めて戦略とは、戦略の実現とは、
システム構築とはといった命題を私は再考させられた。
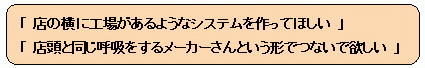
丸川常務の上記言葉は、店舗と工場が一体になって、"靴下"という商品をお客様に供給する仕組みの原点の思想である。
店舗からは工場の状況が見えず、逆に工場からは店舗が見えない状況が普通と考えられる。
最近でこそ、多くの企業が情報システムを整備し、工場と店舗の情報を共有できる環境にあるが、ダンでは随分以前から店舗と工場の密なる連携を意識していた。
さらに、その連携を繋ぐ要はお客様であると位置付けている。
システムにはあまり詳しくない経営トップの "店の横に工場がある"、"店と同じ呼吸をするメーカー" という表現は、
経営課題を的確に掴みこれからのダンはどのような仕組みを作るべきかという方向性が明確に表現されていると思われる。
いわゆる、経営トップの想いでありビジョンが明確になった時点と考えられる。
既に完了した事例ではあるが、経営戦略とシステム化を学ぶ目的でITCプロセスに当てはめて整理してみた。
事例本文より読み取り、事業ドメイン(顧客、ニーズ、コンピタンス)を整理すると図表1のようになる。
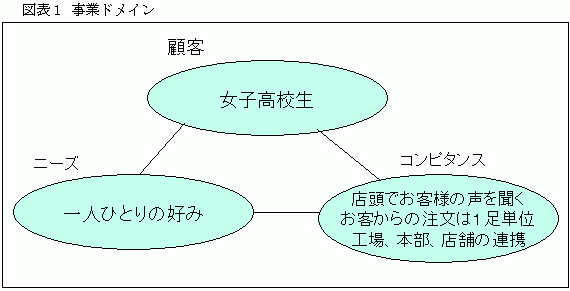
戦略的に顧客を"女子高生"に絞り、その顧客ニーズを"1人ひとりの好み"とし、
それを実現できるコンピタンスは"店頭でのお客様の声を聞く"あるいは"お客からの注文は一足単位"とし"工場、本部、店舗の連携"の仕組みづくりとまとめることができる。
もちろん当初から全体を考慮して進めていたとは考え難いが、全ての要素を的確に表示できる点は、この事例のもつ魅力でもある。
次に、CSF(重要成功要因)を同様に事例本文から探り、図表2のようにまとめてみた。
さらに、私なりにCSFの優先順を考えてみた。上位3項はどれを優先するか悩むところだが敢えて順番付けを行った。
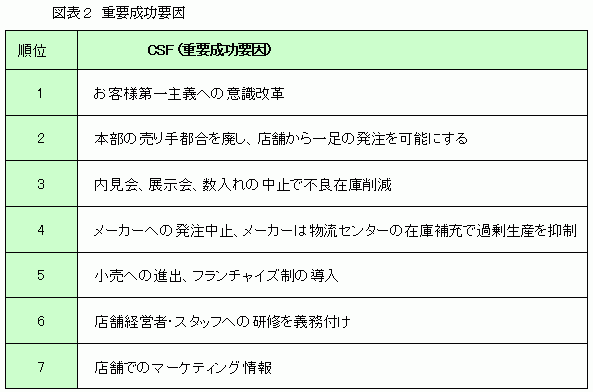
これらのCSF(重要成功要因)はどれも実現が難しいと思われるが、実現できたところにダンの先見性と力強さがあると考える。
最後に、優先順を高くしたCSF(重要成功要因)について、私見を述べる。
「お客様第一主義への意識改革」
お客様第一主義に対してダンは徹底した理念を持っている。事例本文にも書かれているように「お客様第一主義」を理念に掲げる企業は多くある。
しかし経営母体が違う企業が集結したチェーンストアでは、本部と店舗がお客様を共通に認識することが難しい場合が多いように思われる。
特に、フランチャイズチェーンでは本部と店舗が別法人であるため利益の配分は大きな経営課題となる。
お客様第一という大義名分があるが、本来は相反している利益配分は多くの場合、本部の利益確保が優先されているのが現状であろう。
ダンの場合は、"この一足の靴下をお買い上げいただくお客様が、本部からみてもメーカーからみても、糸商からみてもお客様なんだ。
とういう風に社内の教育体制から物の考え方から全部変えました"とある。お客様が明確である。
また、この一足の靴下を買って下さる...とは、誰が本当のお客様であるかを改めて教えられる。
我々はお客様第一主義といいつつも、少しでも多くの売上金額(購入数量の多い)が見込めるお客様を「お客様」と認識しているのではないかと考えさせられた。
「本部の売り手都合を廃し、店舗から一足の発注を可能にする」
"店舗から一足の発注"は、チェーンストア加盟の店舗数が増加し、数がまとまれば可能にもなろうが、
ダンのいう一足とはあくまでもお客様が店舗で買われたその一足を指している。
靴下というアイテムごとの色数が豊富な商品を一足単位で発注を可能にするシステムこそはダンの心骨髄といえる。
ここでは本部の売り手都合を完全に廃している。これはシステムというよりダンのお客様を常に意識した思想そのものと考えられる。
実際に、広陵町にあるダンのSCMセンターを見学する機会を得たが、まさに、店舗からの一足の注文に対して、早朝からパートさんが出荷作業に対応している。
また、センターへ製品を納めるメーカーも同様に店舗から一足の注文に対して種々の作業を進めている。
センターでは一足の発注情報を元にした協業作業を随所に見ることができ、まさに、お客様第一を実感できるセンターとなっている。
「内見会、展示会、数入れの中止で不良在庫削減」
アパレルを中心にした流通業各社が、最も期待を寄せておこなう内見会や展示会、数入れを中止するということは逆転の発想であると考えられる。
内見会や展示会はどのアパレル企業でも売上が読めると信じて、多大な準備期間とコストをかけており、アパレル関係者の一大イベントとなっている。
しかし、あくまでも見込み数や思い込み数であり、予想したほどに売れない結果となっている。
あるいは予想以上に売れて品切れが発生するなど、どの企業でも常に問題となっている。
問題だと認識しつつも、かといって止めることもできないまま、各アパレル企業は毎期同様に繰り返しているの一般的な状況である。
ところが、ダンでは"展示会そのものを止める"と経営判断している。従来の慣習を変えるという、まさに"情報化の前に戦略あり"を実践している。
私は、このたびの事例本文を読み返すにあたり、先ほども記述したが、"IT化を進める前に企業戦略あり"という大命題をダンは我々に伝えている。
さらに、丸川常務というキーマンがいてこそ成し得た情報化の成功事例であると思われる。
この事例が示唆することを実践できるケースに巡り合いたい、ITCとして実践スキルを身に付けたいと考えている。 |
|