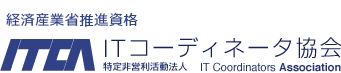3件のコメントありがとうございます。
No.1【2017.12.22】
 |
新里様からのコメント |
|
渋谷会長様 会長ブログを始められて、我々とのコミュニケーションが取れるルートが出来たこと有意義なことと感じます。今後とも末永く続くこと期待します。
2001年度にインストラクター研修を修了して、ITCになって以来17年間ITCとして、内、2003年からは独立ITCとして多大な実践活動をしてきたプロITCです。
「第2の創業計画」ペーパーとご挨拶の動画を視聴しました。先ず、「第2の創業計画」の総論については、私が実践を通して常に同じ問題意識を持ち、実践実行、成果認識、危機感の基本としてきたことが全て盛られていて全く同意、共感するものです。
ITCになって企業や経営者に役立つ仕事をしたいと意気込んで資格を取ったのに、仕事は発掘できないし、協会紹介もないし、個人が勝手に探してビジネスにしろ!では、挫折していくことは同情できますね。これらは協会批判でありません。経営改革をして活性化しようとするITCの使命からみても全く情けない惨状と憂慮の極みです。この度の会長のブログでやっと気づきが見えてきたように思います。
私はOJTトレーナーセミナーの際にも言いましたが、協会とITC全体の劇的改革は次の一点が最重要成功要因です。協会が仕事開拓、企業開拓、ビジネス開拓の市場開拓を強く進める姿勢を明確に出すことです。
プロセスガイドライン知識でなく実践のOJTをキッチリやらなければ、プロになれないし経営者と対等なコンサルが出来ないことを認識していく方向性を協会も持つべきです。だから、OJT施策を打ち出した今年だから、会長から協会の営業力強化、OJTの受講者の弱者救済価格で推進する強固な方針を出して行くことを望みます。
そのためには実戦経験が無い、少ない初心ITCは、OJT施策を通して、IT技術、ノウハウの適用ばかりの視点からでなく、早期にお客様の経営や業務の現状やITリテラシーから、どこからどの程度のIT化、情報化をしみ込ませながら(融合)、業務も組織も、人材能力も改革するか、最善の妥協点を見つけるか、を経験する機会を持てる施策の充実を期待します。
協会、ITC全体の実力向上、市場開拓能力の向上、トレーナーの喫緊の有効活用と成果創出を強く進めなければ、ITCプロと言われるトレーナーの候補も応募が少ないまま、放置したままでは、養成支援の仕事にも付けず次第に魅力は失われ、OJT施策は消えて行ってしまうことになります。
早期にOJTを活性化して、後継者養成をし、ITCのビジネス界での評価を確立していくべきです。この大改革は来年度には、具体的にOJT施策の重点推進が必須と思います。
|
|
|
|
 |
会長からのコメント |
|
新里さん、熱いコメントを有難うございます。「第2の創業計画」の方向性を強くご支援をいただいていること、感謝申し上げます。(昨年、早々にコメントをいただいたのに、遅くなり失礼いたしました。)
おっしゃる通り、ITコーディネータとして、本当に中小企業がITを経営の力とすることができるように支援できる人材を育てるためには、実践訓練の場がもっともっと必要であること、全くその通りだと思います。
カンファレンスでも申し上げたように、中小企業診断士は2度の試験を通っただけでは診断士を名乗ることはできません。先輩診断士が顧問契約をされている企業で5日間コンサルをさせてもらって、徹夜でレポートを書いて経営者に報告して鍛えられるという実践の場を3社分、合計15日間こなして初めて診断士を名乗ることができるという制度をお持ちです。コンサルティングというのは、こういう実践を通じて力を養っていくべきもので、われわれもこのような仕組みをつくっていく必要があると考えています。
同じ問題意識のもと、いろいろご尽力もいただいて「OJT研修」もつくってきましたが、必ずしもスムーズな滑り出しではないこと、ご案内のとおりです。
しかし、これが今後目指すべき方向性であることは確信をしておりますので、何が障壁で、何がクリアすべき課題なのかをしっかり総括をして、実践訓練の場を格段に拡大していきたいと思っております。
また、いろいろお知恵を貸していただけると幸甚です。
|
No.2【2017.12.26】
 |
蔵本様からのコメント |
|
お世話様になります。
普段から感じていることを書かせて頂きます。
ITCの立ち位置とITCとしての武器(ツール、能力)を明確にすべきと思います。
ITCの資格を取得したからといって、ITや経営について特段詳しくなるわけでは有りません。それぞれの専門家の知識にはかないません。
肩書きとして、○○○+ITC(例えば、中小企業診断士+ITC資格、システムエンジニア+ITC資格)といった時に、このITC資格がどういう能力(スキル)を保証しているのか曖昧です。
うたい文句の「IT経営を実現できるプロッフェショナルな人材」とは、どういう能力を持っている者なのか、ITCと非ITCとでは何が違うのかを具体的にかつ自信をもってアピール(差別化)出来るものが必要かと思います(例えば、要求定義、要件定義が適格に出来る人材等)。
こういうところがITC資格を取っても役に立たないと思われる理由の一つかと思います。
最後にITCの立ち位置をはっきりさせる方法のひとつとして、資格の名称を『IT経営コーディネータ』と変えることを提案させて頂きます。
|
|
|
|
 |
会長からのコメント |
|
蔵本さん
ブログへのコメント、ありがとうございます。回答が年をまたぐことになってしまってごめんなさい。
ITCの立ち位置の明確化が必要というご意見をいただいています。蔵本さんが長年のご経験のなかで感じてこられたことと重く受け止めております。
しかしながら、私は、「第2の創業計画」のなかでも、あるいは新年の挨拶のなかでも述べたように、ITコーディネータは経営者と対話を繰り返しながら、経営者が経営課題を具体的かつ論理的に整理するお手伝いをし、そのなかでITをどこでどのように活用するのが効果的なのかを経営者と一緒に考える仕事だと思っておりますし、この立ち位置は唯一無二とも言えるもので、大変価値の高いものだと考えています。だからこそ、私たちは持てる力をフルに発揮して、日本の中小企業がITを経営の力として活かせるように頑張っていかないといけないと「第2の創業計画」を立ち上げました。
最近、あちこちで講演をさせていただく機会に、以下のような図を用いて、ITコーディネータはITの導入そのものだけに関わるのではなく、ITを経営課題のどこでどのように活かすかを一緒に考える仕事で、このプロセスを大事にしないとITを経営の力とすることはできないという話をしておりますが、この反響は大きく、経営者の方々、あるいは経営者と深く関わっている銀行の皆さんから、ITコーディネータがそういう仕事であれば、是非一緒にやってみたいというお声を沢山いただいています。

是非、ITコーディネータの価値を信じて、ご一緒に明るく前向きに進めていければ幸いです。よろしくお願いいたします。
|
No.3【2018.01.07】
 |
横屋様からのコメント |
新年あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
昨年、静岡で頑張っている独立系のITC Kさんとお酒を飲みながら話す機会がありました。彼のITCとしての活動は、まさに会長が言うように、ショートタームのリターンを求めない、ボランティアやプロボノ活動ではないですが、地道で丹念な町医者的な取り組みです。このような活動をとおして中小企業経営者の懐に入り、信頼を勝ち取る。その結果が「ITCになってから雌伏10年、ようやく芽が出ました」と。Kさんは感慨深げに話しをしてくれました。
私の下記ブログでも、「見直そう! ITコーディネータ」のタイトルで、上記の内容を書いてあります。
ご参考までに
|
|
|
|
 |
会長からのコメント |
|
おめでとうございます。
小生の新年の挨拶ブログに対して、しっかりフォローいただき、長年継続されている横屋さんのブログにも大きく取り上げていただき、本当にありがとうございます。
今更ですが、11月にも私の「トリムタブ」の話を取り上げてくださっていますね。いつもご支援いただき、とても心強いです。
横屋さんの趣味は、私と同じ自転車。福井でも金沢でも颯爽と自転車を乗り回しておられ、いつまでもお若い横屋さんを今年もしっかり見習って、自転車と、そして「第2の創業計画」のペダルを一歩一歩着実に漕いで行きたいと思います。今年もよろしくお願いいたします。
|