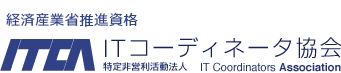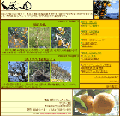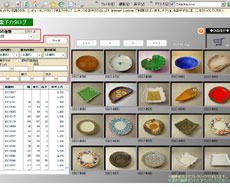| 販売促進 ~ 店舗の強みを探り、Webサイトの戦略活用へ ~
始まりはITに対する素朴な疑問だった 神奈川県横浜市、歌謡曲「伊勢佐木町ブルース」で知られる伊勢佐木町商店街に店舗を構えるプリンスは、県内に4店舗を持つ高級紳士服洋品店である。イタリア製を中心にした上質な品揃えが特徴で、購買力のある比較的高い年齢層が主要顧客だ。 バブル時には店舗を15まで拡大した同社も、バブル崩壊による経済の冷え込みや紳士服の低価格化により、同程度の売上を維持するのは困難な状況になった。吉田親弘社長は店舗数を絞るなどのリストラを行い安定利益を確保したが、最近になって一つのことが気にかかりだした。 それは、「世の中はIT、ITと言うが、いったい何なのか、IT化に乗り遅れるとこれから会社をやっていくこともできなくなるのではないか」という不安だった。 ITに明るい世代である息子さんからの勧めもあって、店舗経営にITを活用しようと有名ショッピングモール「楽天」に出品を試みる。反応はあったものの思ったほどには売れず、どうしたものかと悩みは深まる。ITベンダーの営業はひっきりなしにやって来るが自社の製品を売ろうとするだけ。自分の疑問に答えてくれる相手にはならなかった。 そんなころ、横浜商工会議所の研修会を契機に中立な立場でIT活用の相談にのってもらえるITコーディネータの存在を知る。ITCなら自分の疑問に答えてもらえるかもしれないと期待をもった吉田社長は、手始めに、3分の1の費用負担でアドバイスが受けられるIT推進アドバイザー派遣制度を使い、コンサルティングを依頼することにした。 ITコーディネータとともに会社を客観的に分析 ITコーディネータの小野敏夫氏と大西和志氏は、いきなりWebサイトの改訂を提案するのではなく、基本に戻ってまずは経営状況の分析に着手した。吉田社長とともに同社の現状を整理し「特にプリンスの強みはどこなのかを実際に各店舗を見ながら探っていった」(ITC小野氏)という。 同社は、吉田社長が社内で育てた店長たちがそれぞれ個性を発揮して店舗経営を行っている。その結果、顧客との強い関係が築かれており、年間数10万円の買い物をする固定客をつかんでいることが大きな強みだった。しかし顧客は自然と高齢化していき、その数は減ってしまう。現在の顧客層に続く次の固定客をどう開拓していくかが同社の課題として浮き彫りになってきた。 吉田社長の直接的な悩みがホームページの改善だったこともあり、IT活用の具体的な行動はホームページのリニューアルからスタート。店舗での接客が強みの同社の特徴を活かすべく、Webサイトでは洋服を売ることよりも来店を誘導することを目的に「プリンスのファッション・コーディネート力を見せる「トータルコーディネート」サイト」(ITC大西氏)の構築を目指した。 リニューアル途中で、早くも顧客開拓成果が パソコンの導入からネットワークの整備といった設備準備、またWebページで提案するコーディネート例を自ら撮影し、自力でWebサイトを作成する作業まで......。現在同社は、ITCと共にIT活用による改革のステップを一歩ずつ歩んでいるところだ。 Webサイトの改訂方針が明確になった後、一時的な措置として旧来のサイトを一部改良してみたところ、北海道から「掲載した服を一式欲しい」という問合せがきたり、常連顧客がホームページのURLを口コミの資料として使い新規顧客を紹介してくれたりなど、早くも効果が表れた。本格リニューアルが完了すれば、顧客開拓への新しい道が開けるのも間違いないだろう。 吉田社長はこの経験を通じて「ITというものが少しずつわかってきた」という。今後もITCのアドバイスを受けながら、さらに改革を進めて行きたいとのことだ。
<ITコーディネータを活用してどうでしたか?> 「ITは、一人でやろうと考えない方が良い」 ITを使わないと時代に取り残されてしまうという思いがあったものの、何をすればよいのかがわかりませんでした。 ITコーディネータは何でも聞けるアドバイザーでもあり、日々、進歩を見ていてくれるサポーターでもあります。このプロセスを通じて、ITというものの価値が少しずつ見えてきました。 経営者は自分一人でITをやろうなどと考えない方がよい。良い相談相手を作ることが有効だと思います。 <IT推進アドバイザー派遣事業とは?> 中小企業基盤整備機構が実施している制度。この制度を利用すると、派遣費用の3分の2が補助され、1日1万5000円の費用負担でアドバイザーのコンサルティングが受けられる。本事業への申し込みはITコーディネータ協会でも受けつけている。「IT推進アドバイザー派遣事業」の詳細はこちら >> |
||||||||||||||||||||||||